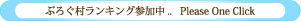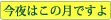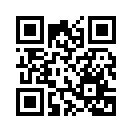2010年04月08日
指さし地蔵(不来坂)

宇久須(うぐす)と安良里(あらり)を結ぶ一本の道。
昔は海路を除けば陸道はこの「不来坂(こじがさか)」だけ。
大人も子どもも越えていった峠道。
その垰(たわ)で道中の安全を見守っていてくれた地蔵さん。
それが「指さし地蔵」です。
いつの間にか、その存在が忘れ去られてしまっていました。
安良里のお爺に聞くと
「宇久須の登り口に降ろしてある」
「まだ垰の上にちゃんとある」
「安良里の川の縁に置かれている」
「誰かが持って行ったきり出てこない」
などいろいろな話がでてきました。
今回、どうしても探し出してみたいという強い気持が...
不来坂を宇久須から登り、安良里へ下りましたが見つかりません。
一度は断念して車へ戻り帰途へ。
その時に畑の人に出合ったのがラッキーでした。
ふと、聞いてみれば…
「あっ確か、○○のそばにあったようだな」
はい、そのまま安良里にUターン。
言われた場所を隈なく探してはみたものの…ありません。
やっぱり駄目か…と諦めそうになった時に近くの民家の窓がガラガラ。
理由を話してみると、もしかしたらこれかしら…と。
わざわざ出てきてくれて指を差された場所は、なんと工事用の器材置場。
その中に何か石のようなものが無造作に置かれている、というよりも投げられている。
「んん?もしかして」
と、広げられた脚立の上に載せられた土嚢をどかして、脚立をどかすと四角い明らかに石仏らしき石が。
ゆっくり丁寧に起こしてみると、なんと指の彫り物がしっかりと残ったものが。
これじゃないですか、指さし地蔵さん。
信じられない事ですが、この彫刻側をコンクリート地面にして置かれていました。
工事現場の乱雑な扱いに言葉も出ません。
こんなものなのでしょうか…
カネジョウさんと相談した結果、その状況を何とかしてもらうためには教育委員会へ相談しようということに。
安良里にある西伊豆町教育委員会。
担当された方は、不来坂も指さし地蔵の知識もなく初めから説明いたしました。
危機感が伝わったかどうか、わかりませんが現場を見てもらうことに。
工事関係者に「しっかりと伝えておきます」とのこと。
一度、破壊されてしまえば再生不可能。
この重大性がわかっていれば即、移動するなりの手段を取って欲しかったです。
田舎ってどこもこんなものなのでしょうか?
無くなってからでは遅すぎるのですけど_?
将来、傷も無く無事であることを祈ります………
2010年04月08日
廃道復活への道「不来坂」

【不来坂の峠にて】
町村合併で西伊豆町になるまでは宇久須と安良里は6年前まで賀茂村でした。
道路が開通するまでは、その賀茂村でもお互いに行き来するためには山越えをしなければなりませんでした。
宇久須と安良里とを最短距離で結ぶ峠。
『不来坂(こじがさか)』
国道ができてからは誰も通る人もいなくなり記憶から忘れ去られている峠道。
いつか、全部歩きぬけようと思っていました。
そして昨日、とうとう決行。
カネジョウさんと歩いてきました。

宇久須側から登り始めると対岸に何やら掘られています。
防空壕にしては人里から離れ過ぎている…
鉱山を掘った跡なのでしょうか?

道は下草に覆われて不明瞭になっています。
時々、ルートファインディングが必要です。
このままでは間違いなく道迷いすること必至…
今のところは場所は公開できない状態です。
そして、いきなり目の前に現れた洞窟。
下には水が溜まっています。

その昔、不来坂には二本松があって、それは目立ったという話を聞いていました。
その二本松は、なんと終戦の日に倒れたという不思議な話もあって、かなり興味を魅かれた峠でもありました。
その松の倒木も発見。
半分腐りかけてはいますが、しっかりと二本ありました。
噂は事実だった事が判明いたしました。

もう一本の松の残骸です。
かなりの太さがあり、相当年数が経っていた立派な松の木だったのでしょう。
往年が偲ばれます。

峠までは杉の植林が続いていました。
超えると安良里側。
こちらは広葉樹林帯の明るい斜面が続いていました。
こちらも道は荒れていて、どこが本道であるのかを確認しながら下ります。
露岩が多く、浮き石だらけの道はかなり危険。
しばらく下ると石垣が現れました。
戦時中はこの辺りも畑を作っていたのでしょう。
先人の苦労が伝わってくる、そんな場所です。

開けた沢筋になると一気に視界が広がります。
安良里の港が一望できます。
下界の音も風に乗って良く聞こえだします。
ここまで下ればもう、僅かの距離。
ツワブキが群生する河原を歩くと集落の外れに。
今回は、車を入山口にデポしておいたので、960mのトンネルをひたすら歩くことに…
トラックの排ガスが溜まるトンネルの出口は遠い…
ですが、旧道を登った感激を味わいながらなので大丈夫(笑)