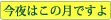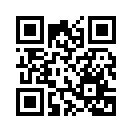2007年11月19日
飛騨で見つけた素敵(2)
清見の山村には、たくさんの資源(たからもの)が埋まっていました。
古き善きもの。
新しいものが、すべて良いなんてのは間違った考え方ですね。
早速、こんな水船を見つけました。
水を大切にしながら、昔からの知恵ですね。
木をくり抜いて桶のようにしています。
このような水屋は、ほとんどの家の入り口に設置されていました。
そして2枚目の写真は、桶が2段になっています。
高い場所の桶ではあまり汚れていないものを洗い、下では泥がついたものを洗う。水を大事に使う知恵ですね。


屋根の瓦?
普通の瓦ではありません。栗の木など堅く腐りにくい木材を重ねて瓦のようにしています。これも重い瓦を使うよりも軒先には勝手が良いのでしょう。
探し始めると、多くの家で使われていました。

清見集落の、「春日神社」。
写真を良く見ると、鳥居にかけられている注連縄が弛んでいるのが判りますでしょうか?
この注連縄は、弛んだのではなく、わざと弛ませています。
「なぜ?」
鳥居をくぐるときに、頭を下げないと通れません・・。
なるほど。

いちいの木に赤い実を見つけました。
この実は、甘くてちょっとゼリーっぽい味です。
種は「タキシン」を含むので食べてはダメです。

そして、この地は高山と京都方面と通じる郡上街道の国境。
出入りする人の手形を調べたり、荷物にあわせて税金を取り立てたりする番所が江戸時代には置かれていたのだそうで、今も「口留番所跡」として残されています。

まだまだ、カタクリの群生地や、白い岩つつじの栽培農家があったりと見所たくさんです。きっと、パスカル清見の中川さんが地域案内プログラムを作ってくれるでしょう!(ちょいとプレッシャーかけて)。皆さんも、せせらぎ街道を走る時は、パスカル清見で泊まってみては?料理は、とっても美味しい(これ驚くほどです!)。食べ過ぎ注意報発令中です・・・
古き善きもの。
新しいものが、すべて良いなんてのは間違った考え方ですね。
早速、こんな水船を見つけました。
水を大切にしながら、昔からの知恵ですね。
木をくり抜いて桶のようにしています。
このような水屋は、ほとんどの家の入り口に設置されていました。
そして2枚目の写真は、桶が2段になっています。
高い場所の桶ではあまり汚れていないものを洗い、下では泥がついたものを洗う。水を大事に使う知恵ですね。


屋根の瓦?
普通の瓦ではありません。栗の木など堅く腐りにくい木材を重ねて瓦のようにしています。これも重い瓦を使うよりも軒先には勝手が良いのでしょう。
探し始めると、多くの家で使われていました。

清見集落の、「春日神社」。
写真を良く見ると、鳥居にかけられている注連縄が弛んでいるのが判りますでしょうか?
この注連縄は、弛んだのではなく、わざと弛ませています。
「なぜ?」
鳥居をくぐるときに、頭を下げないと通れません・・。
なるほど。

いちいの木に赤い実を見つけました。
この実は、甘くてちょっとゼリーっぽい味です。
種は「タキシン」を含むので食べてはダメです。

そして、この地は高山と京都方面と通じる郡上街道の国境。
出入りする人の手形を調べたり、荷物にあわせて税金を取り立てたりする番所が江戸時代には置かれていたのだそうで、今も「口留番所跡」として残されています。

まだまだ、カタクリの群生地や、白い岩つつじの栽培農家があったりと見所たくさんです。きっと、パスカル清見の中川さんが地域案内プログラムを作ってくれるでしょう!(ちょいとプレッシャーかけて)。皆さんも、せせらぎ街道を走る時は、パスカル清見で泊まってみては?料理は、とっても美味しい(これ驚くほどです!)。食べ過ぎ注意報発令中です・・・
Posted by 鈴木達志 at 09:09│Comments(0)
│グリーン・ツーリズム
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。