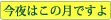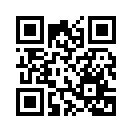2007年05月15日
解説登攀用語
5/13に書きました「城山クライミング」で専門用語だらけで良くワカラン
というクレームがありました(スミマセンです)。ので・・・解説つけます....

フリークライミング (⇔エイドクライミング)
人工的な登攀用具(アブミ(簡易はしご)などを使わずに、手足で岩を
攀じ登る方法。一番、手軽で、かつ達成感もあります。
今やクライミング=フリークライミングとなっています。ちなみに、安全
確保のためのロープは必ず使用しますよ。ロープなしで落ちたら・・・
でしょ?
ヨセミテ
アメリカのヨセミテ国立公園のこと。クライマーにはヨセミテ=クライミ
ングで浸透しています。ヨセミテヴァレーと呼ばれる渓谷には、ハーフ
ドームと言われる大岸壁などがあり、花崗岩の一枚岩はクライマーの
憧れです。
岩と雪
日本を代表するクライミング専門誌。山と渓谷社から発行されていま
したが、極々少数のマニアの購読者しかいなかったため、惜しまれな
がら廃刊・・・100号記念誌には、私の書いた「湯河原:茅ヶ崎ロック」
の記事が掲載されています。
ビムラム底
登山靴のソールの代表メーカー。というよりも独占企業。スリップし
にくいパターンは、昔も今も殆ど変わらない・・・。高級登山靴には、
ビムラムが当たり前・・・です。
クレッターシューズ
岩を攀じるためにだけに設計開発された登山靴。足首は殆ど曲がら
ずに、昔風の攀じりかたの「岩に対して正対」で登る。限りなく細めに
作られた足形は、靴が人を選ぶ。ちなみに私は履けるメーカーはあ
りませんでした。外国人の足が羨ましい・・・(甲高だんびろ、プラス
軟骨もちですぅ)
EBシューズ
現代のクライミングシューズの原型。当時はマジックシューズともい
われ、これがあれば、登れるグレード(岩の難しさによって決められ
る)が上がると言われていました。皮と厚手のコットンでできていて
蒸れ蒸れ。水虫に悩まされたクライマー多数。しかし、現代のものと
比較すると、骨董品?のデザイン。性能は飛躍的に向上中。
アメリカのたかが若者の遊び
ロン毛に上半身裸、きったない擦り切れたTシャツや短パンのヤンキ
ーは、品行方正で山男=まじめなしっかりとした誠実な賢人と認識
されていた日本山岳関係者には、まさしくヒッピーと映ったに違いな
い。
土曜日は自主休業
今の週休2日制が羨ましすぎるぅ!もっと遅くに生まれていたら、こ
の恩恵に与れたのに・・・。土曜日の授業は「代返」に頼ってました。
でも留年もせずに3年で卒業。先生、ありがとう・・・感謝...
室内壁
クライミングジムという、当時はクライマーが練習の為に通った場所。
ボードもしくはコンクリートに、ホールド(手や足をかけるためのもの)
をボルトで止めてあり、クライミングを行うのです。90度以上に角度
がつけられていたりしてトレーニングには最適。落ちても抜ける心配
のないボルトで確保するため、ちっとやそっとのアクロバットだって
問題なし。近頃はオソトの岩場には興味が無く、ひたすらスポーツと
して室内壁で遊ぶ方々が多い。クライミング=危険という図式はなり
たたなくなりました。
城ケ崎
いわずと知れた東伊豆の八幡野城ヶ崎海岸です。溶岩が海に流れ
込む際に急激に冷やされ切り立った断崖絶壁になっています。周遊
道が作られていて、灯台下にある吊橋は観光客に有名スポットです。
その断崖絶壁にアホな私のようなクライマーが集合。観光客から
見下ろされて「変な人」と指差されることに喜びを感じつつ、遊んでい
ます。岩の割れ目(クラック)が多く、この割れ目に手や足を突っ込ん
で、くさびとしながら攀じ登ります。ですから、クライマーは自虐精神
が豊富。簡単に言うとマゾなんですね。
城山南壁
城山を見上げた時に、一番広い岩の面積がある所を指します。南面
に面してもいますので、名前通りですね。このあたりを良く探すと、何
か張り付いているものが見えるときが多いです。スパイダーマンでは
ありません。ただの高所作業愛好家。この城山は夏は、うだるほど暑。
熱中症の危険にさらされながら登っています。ビノキュラー(双眼鏡)
で覗けば、おサルたちの遊びが良く見えます。アピタの屋上あたりか
らがベストビューです。
フェース
顔ではありません。一枚岩の壁のことを指します。どうも、のっぺりと
した顔からイマジネーションしていただければ完璧です!遠くから見る
とツルツルに見える南壁も、近くから見れば ”あばたにえくぼ” です。
この、あばたとえくぼに手足を乗せながら登ります。
2ピッチ
クライミングロープ(昔風に言えばザイルですね)は40メートルが基
本でした(でしたと言うのは今は45,50メートルなど、そのクライミン
グのやり方によって選べる時代になったからです)。その40メートル
弱登りきると、1ピッチと数えます。ルートが入り組んだり、確保地点
によって、その限りではありませんが・・・。
鎌形ハング
農家の方には当たり前の道具「鎌」。弓形のような形をしています。
同じような形をしているのでネーミングされたものを思います。ハング
というのは、 「庇(ひさし)」 状になった屋根のような部分です。つ
まり、空中にせり出している部分で、ここを登るのは一旦、足が壁か
ら離れないとならなくなります。高度感たっぷりでサーカス芸のよう
なアクロバティックな曲芸をするのは、自分のアドレナリンとの戦い
ですね。鎌形の隣には隣には三日月ハングってのもあります・・・。
ハーケン
岩の割れ目(リスといいます)に鉄のくさび状の物をハンマーで叩き
込んで、しっかりと銜え込ませます。しっかりと打ち込んでしまえば
岩が広がらない限りは、結構体重を支えてくれますが、誰が打った
か分からないハーケンを使うのは躊躇するところ・・・です。ちなみに
しっかりと打ち込んでいくと「キーン」と乾いた音がしてきます。
頭の部分には穴が開いていて、カラビナという金属の環のようなもの
を入れ、ロープを通すことによって、もしも落ちちゃった・・場合は、
ココを始点にして止まります(抜けちゃったら、下の支点までぶっと
びますが)。えてして希望的観測であるハーケンが多くいちかばちか
の雰囲気を醸し出しているルートが多々あります・・・
ボルト
ハーケンとは違って、岩に割れ目がないような場所は、岩にドリルで
穴をあけて、金属の環っかを打ち込みます。厳密に言えば自然破壊
なのですが、安全の為に見てみないふりをしているのが現状です。
フリークライミングが、クリーンクライミングを呼ばれた時代、イヴォン
ショイナードさん(パタゴニアの社長さんですよ)とダーティなイメージ
キャラクターの○○氏との戦いもありましたケド・・・
以上でありました・・・
というクレームがありました(スミマセンです)。ので・・・解説つけます....

フリークライミング (⇔エイドクライミング)
人工的な登攀用具(アブミ(簡易はしご)などを使わずに、手足で岩を
攀じ登る方法。一番、手軽で、かつ達成感もあります。
今やクライミング=フリークライミングとなっています。ちなみに、安全
確保のためのロープは必ず使用しますよ。ロープなしで落ちたら・・・
でしょ?
ヨセミテ
アメリカのヨセミテ国立公園のこと。クライマーにはヨセミテ=クライミ
ングで浸透しています。ヨセミテヴァレーと呼ばれる渓谷には、ハーフ
ドームと言われる大岸壁などがあり、花崗岩の一枚岩はクライマーの
憧れです。
岩と雪
日本を代表するクライミング専門誌。山と渓谷社から発行されていま
したが、極々少数のマニアの購読者しかいなかったため、惜しまれな
がら廃刊・・・100号記念誌には、私の書いた「湯河原:茅ヶ崎ロック」
の記事が掲載されています。
ビムラム底
登山靴のソールの代表メーカー。というよりも独占企業。スリップし
にくいパターンは、昔も今も殆ど変わらない・・・。高級登山靴には、
ビムラムが当たり前・・・です。
クレッターシューズ
岩を攀じるためにだけに設計開発された登山靴。足首は殆ど曲がら
ずに、昔風の攀じりかたの「岩に対して正対」で登る。限りなく細めに
作られた足形は、靴が人を選ぶ。ちなみに私は履けるメーカーはあ
りませんでした。外国人の足が羨ましい・・・(甲高だんびろ、プラス
軟骨もちですぅ)
EBシューズ
現代のクライミングシューズの原型。当時はマジックシューズともい
われ、これがあれば、登れるグレード(岩の難しさによって決められ
る)が上がると言われていました。皮と厚手のコットンでできていて
蒸れ蒸れ。水虫に悩まされたクライマー多数。しかし、現代のものと
比較すると、骨董品?のデザイン。性能は飛躍的に向上中。
アメリカのたかが若者の遊び
ロン毛に上半身裸、きったない擦り切れたTシャツや短パンのヤンキ
ーは、品行方正で山男=まじめなしっかりとした誠実な賢人と認識
されていた日本山岳関係者には、まさしくヒッピーと映ったに違いな
い。
土曜日は自主休業
今の週休2日制が羨ましすぎるぅ!もっと遅くに生まれていたら、こ
の恩恵に与れたのに・・・。土曜日の授業は「代返」に頼ってました。
でも留年もせずに3年で卒業。先生、ありがとう・・・感謝...
室内壁
クライミングジムという、当時はクライマーが練習の為に通った場所。
ボードもしくはコンクリートに、ホールド(手や足をかけるためのもの)
をボルトで止めてあり、クライミングを行うのです。90度以上に角度
がつけられていたりしてトレーニングには最適。落ちても抜ける心配
のないボルトで確保するため、ちっとやそっとのアクロバットだって
問題なし。近頃はオソトの岩場には興味が無く、ひたすらスポーツと
して室内壁で遊ぶ方々が多い。クライミング=危険という図式はなり
たたなくなりました。
城ケ崎
いわずと知れた東伊豆の八幡野城ヶ崎海岸です。溶岩が海に流れ
込む際に急激に冷やされ切り立った断崖絶壁になっています。周遊
道が作られていて、灯台下にある吊橋は観光客に有名スポットです。
その断崖絶壁にアホな私のようなクライマーが集合。観光客から
見下ろされて「変な人」と指差されることに喜びを感じつつ、遊んでい
ます。岩の割れ目(クラック)が多く、この割れ目に手や足を突っ込ん
で、くさびとしながら攀じ登ります。ですから、クライマーは自虐精神
が豊富。簡単に言うとマゾなんですね。
城山南壁
城山を見上げた時に、一番広い岩の面積がある所を指します。南面
に面してもいますので、名前通りですね。このあたりを良く探すと、何
か張り付いているものが見えるときが多いです。スパイダーマンでは
ありません。ただの高所作業愛好家。この城山は夏は、うだるほど暑。
熱中症の危険にさらされながら登っています。ビノキュラー(双眼鏡)
で覗けば、おサルたちの遊びが良く見えます。アピタの屋上あたりか
らがベストビューです。
フェース
顔ではありません。一枚岩の壁のことを指します。どうも、のっぺりと
した顔からイマジネーションしていただければ完璧です!遠くから見る
とツルツルに見える南壁も、近くから見れば ”あばたにえくぼ” です。
この、あばたとえくぼに手足を乗せながら登ります。
2ピッチ
クライミングロープ(昔風に言えばザイルですね)は40メートルが基
本でした(でしたと言うのは今は45,50メートルなど、そのクライミン
グのやり方によって選べる時代になったからです)。その40メートル
弱登りきると、1ピッチと数えます。ルートが入り組んだり、確保地点
によって、その限りではありませんが・・・。
鎌形ハング
農家の方には当たり前の道具「鎌」。弓形のような形をしています。
同じような形をしているのでネーミングされたものを思います。ハング
というのは、 「庇(ひさし)」 状になった屋根のような部分です。つ
まり、空中にせり出している部分で、ここを登るのは一旦、足が壁か
ら離れないとならなくなります。高度感たっぷりでサーカス芸のよう
なアクロバティックな曲芸をするのは、自分のアドレナリンとの戦い
ですね。鎌形の隣には隣には三日月ハングってのもあります・・・。
ハーケン
岩の割れ目(リスといいます)に鉄のくさび状の物をハンマーで叩き
込んで、しっかりと銜え込ませます。しっかりと打ち込んでしまえば
岩が広がらない限りは、結構体重を支えてくれますが、誰が打った
か分からないハーケンを使うのは躊躇するところ・・・です。ちなみに
しっかりと打ち込んでいくと「キーン」と乾いた音がしてきます。
頭の部分には穴が開いていて、カラビナという金属の環のようなもの
を入れ、ロープを通すことによって、もしも落ちちゃった・・場合は、
ココを始点にして止まります(抜けちゃったら、下の支点までぶっと
びますが)。えてして希望的観測であるハーケンが多くいちかばちか
の雰囲気を醸し出しているルートが多々あります・・・
ボルト
ハーケンとは違って、岩に割れ目がないような場所は、岩にドリルで
穴をあけて、金属の環っかを打ち込みます。厳密に言えば自然破壊
なのですが、安全の為に見てみないふりをしているのが現状です。
フリークライミングが、クリーンクライミングを呼ばれた時代、イヴォン
ショイナードさん(パタゴニアの社長さんですよ)とダーティなイメージ
キャラクターの○○氏との戦いもありましたケド・・・
以上でありました・・・
Posted by 鈴木達志 at 15:59│Comments(0)
│登山・クライミング
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。