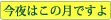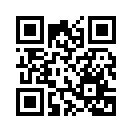2007年12月07日
民話「永明寺の子安さん」
「永明寺の子安さん」。【地図】
西伊豆町宇久須の永明寺に伝わる民話です。
<カネジョウさんの文書を引用しています>
 【永明寺の銀杏】
【永明寺の銀杏】
永明寺の本道の間に小安像が安置されています。木製で高さが約90cm。胸に赤ちゃんを抱いて、温かで柔和なお顔をしています。
「永明寺の子安さん」と呼ばれていて、ご近所の人たちに親しまれています。「安産を見守り、子どもの健やかな成長を助けてくれる」という観音様です。子宝に恵まれるようにと、お参りに来る人も多くいます。

昔は、仁科や大沢里の人たちは子安さん参りのために、大久保の「やしゃばら峠」を越えてきました。そして願い事を紙に書いて、境内の大銀杏に結び付けて帰られたそうです。子安さんは、子安神とか子安地蔵とも呼ばれ、仏様でもあり神様としても祀られています。時々、しきみに代えて榊を供えていうことがあります。

清和、陽成、光孝天皇の御代の歴史書、三代実録には、美濃の国子安神という記述があり、子安さんは式外古神とされています。神社は式内社といい延喜式神名帳に記載されています。
したがって子安さんは、式外古神として仏教伝来以前にも、妊婦の安産を守る子安信仰の対象として存在していたと考えられます。
子どもが安らかに生まれることを願う心情は、未来永劫つながるものですので、宗教においても子安信仰が存在することは当然の理です。

永明寺の子安像は文化十一年(1814年)の棟札によると、もとは大久須に、中の堂があり、同年七月、山口県三田尻村の行者、作次郎が今の像を彫刻し安置したということが、永明寺住職の仁寛尚の撰文に記してあります。子安像を祀っていた中の堂は、永明寺の管轄下にあったのでしょう。
堂の荒廃が酷くなり明治の初めに、永明寺に移されました。大正十三年九月、現在のものに再興されたとのことです。
西伊豆町宇久須の永明寺に伝わる民話です。
<カネジョウさんの文書を引用しています>
 【永明寺の銀杏】
【永明寺の銀杏】永明寺の本道の間に小安像が安置されています。木製で高さが約90cm。胸に赤ちゃんを抱いて、温かで柔和なお顔をしています。
「永明寺の子安さん」と呼ばれていて、ご近所の人たちに親しまれています。「安産を見守り、子どもの健やかな成長を助けてくれる」という観音様です。子宝に恵まれるようにと、お参りに来る人も多くいます。

昔は、仁科や大沢里の人たちは子安さん参りのために、大久保の「やしゃばら峠」を越えてきました。そして願い事を紙に書いて、境内の大銀杏に結び付けて帰られたそうです。子安さんは、子安神とか子安地蔵とも呼ばれ、仏様でもあり神様としても祀られています。時々、しきみに代えて榊を供えていうことがあります。

清和、陽成、光孝天皇の御代の歴史書、三代実録には、美濃の国子安神という記述があり、子安さんは式外古神とされています。神社は式内社といい延喜式神名帳に記載されています。
したがって子安さんは、式外古神として仏教伝来以前にも、妊婦の安産を守る子安信仰の対象として存在していたと考えられます。
子どもが安らかに生まれることを願う心情は、未来永劫つながるものですので、宗教においても子安信仰が存在することは当然の理です。

永明寺の子安像は文化十一年(1814年)の棟札によると、もとは大久須に、中の堂があり、同年七月、山口県三田尻村の行者、作次郎が今の像を彫刻し安置したということが、永明寺住職の仁寛尚の撰文に記してあります。子安像を祀っていた中の堂は、永明寺の管轄下にあったのでしょう。
堂の荒廃が酷くなり明治の初めに、永明寺に移されました。大正十三年九月、現在のものに再興されたとのことです。
Posted by 鈴木達志 at 18:42│Comments(0)
│宇久須
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。