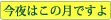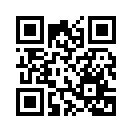2007年05月03日
奇岩「雨降り石」(民話伝承)
【安良里の民話シリーズ 1】
奇岩「雨降り石」
黄金崎クリスタルパークを越えてトンネルを出ると海が
すぐ横に広がります。
ここが安良里の坂本海岸です。夏には海水浴場となって
安良里の子どもたちの遊び場になります。
目の前には弁天島があり、詩的な風景を醸し出しています。
この海岸に、凝灰岩の円筒形の大きな岩の塊があります。
この岩が「雨降り岩」と呼ばれ、民話が伝承されています。
高さは約4メートル。見上げる場所に約60cmほどの丸い穴が
あって、ここを目掛けて石を投げ込み、雨乞いをしたのだそうです。

 《ここ》
《ここ》
安良里のヒデさん(76歳)に聞いた話では、ヒデさんが子どもの
頃でも雨乞いした記憶は無いそうです。
相当、昔にこの儀式は執り行われなくなったのでしょうね。
伝承では、祭事の方法が記されています。
雨が無く水不足が長く続くと、村の衆が集まり、九つ半刻(13時)頃より
薪に点火、薪をどんどんくべていって、大火にしていきます。
夕暮れ時に、手甲脚絆に蓑笠を着けた田植え姿の祭主が、雨乞い岩に
登り、祭主を目掛け、雨に擬した水を掛けつつ、雨乞い岩をお清めします。
雨乞い岩から祭主が降り、丸い穴を祈念し、小石を投げ込みます。
村の衆全員も続いて投げ入れます。
丸穴に入った小石が少しであれば、小雨が期待でき、数多く入るほどに
大雨がやってくると言われています。
言い伝えでは、祭事の後には必ずの雨が降ったと言われています。
さらに、このような記述もあります。
安良里の宮崎覚治郎(故人)さんからの語り口...
『梯子は掛けないサ、坂本へ遊びに行くと、この岩に登るのが子供の
時の遊びだったニ、上はわりあい平らだニ、ア、本当だ、試してみたら
簡単に登れた。祝詞は無かったナー、大火を長く焚くほど御利益があ
ると、古い衆はいったナー、水をかける役は俺ーやる。俺ーやると騒ぎ
だが、蓑笠を着ける役は皆んながヤダがったナー、汝ーやれ、お前が
やれといろいろやったが、みんな逃っ尻をかまえていてやりたがらなか
ったナー、仕様がなくて「ヨシダ」の爺さんに頼んでやってもらったのサ。
それが終いには「ヨシダ」の爺さんの役のようになったナー。今のように
色々の入れ物も無かったし、手桶で水をかけたが、そこまであまり届か
なかったニ、若い衆は爺さんが岩から降りて来ると「オマケ」だといって、
また浴びせかけて面白がったニ。
ある日、今日昼から雨乞いをやろうじゃと、話があったが、こんな日にや
ったって雨なんか降るもんか、といって出ずに居たら、後で八分にあっ
たニ』
安良里の藤井寅吉(故人)さんの語り口...
『アノ岩は大部埋まったニ、まァだ三尺(約1メートル)位い高かったナー
雨乞いの話は聞いているが、俺ァ、あっこでやった覚えはないナー』
資料は宇久須の海鮮焼き「かねじょう」店主の浅賀丈吉さんからお借りしました。
奇岩「雨降り石」
黄金崎クリスタルパークを越えてトンネルを出ると海が
すぐ横に広がります。
ここが安良里の坂本海岸です。夏には海水浴場となって
安良里の子どもたちの遊び場になります。
目の前には弁天島があり、詩的な風景を醸し出しています。
この海岸に、凝灰岩の円筒形の大きな岩の塊があります。
この岩が「雨降り岩」と呼ばれ、民話が伝承されています。
高さは約4メートル。見上げる場所に約60cmほどの丸い穴が
あって、ここを目掛けて石を投げ込み、雨乞いをしたのだそうです。

安良里のヒデさん(76歳)に聞いた話では、ヒデさんが子どもの
頃でも雨乞いした記憶は無いそうです。
相当、昔にこの儀式は執り行われなくなったのでしょうね。
伝承では、祭事の方法が記されています。
雨が無く水不足が長く続くと、村の衆が集まり、九つ半刻(13時)頃より
薪に点火、薪をどんどんくべていって、大火にしていきます。
夕暮れ時に、手甲脚絆に蓑笠を着けた田植え姿の祭主が、雨乞い岩に
登り、祭主を目掛け、雨に擬した水を掛けつつ、雨乞い岩をお清めします。
雨乞い岩から祭主が降り、丸い穴を祈念し、小石を投げ込みます。
村の衆全員も続いて投げ入れます。
丸穴に入った小石が少しであれば、小雨が期待でき、数多く入るほどに
大雨がやってくると言われています。
言い伝えでは、祭事の後には必ずの雨が降ったと言われています。
さらに、このような記述もあります。
安良里の宮崎覚治郎(故人)さんからの語り口...
『梯子は掛けないサ、坂本へ遊びに行くと、この岩に登るのが子供の
時の遊びだったニ、上はわりあい平らだニ、ア、本当だ、試してみたら
簡単に登れた。祝詞は無かったナー、大火を長く焚くほど御利益があ
ると、古い衆はいったナー、水をかける役は俺ーやる。俺ーやると騒ぎ
だが、蓑笠を着ける役は皆んながヤダがったナー、汝ーやれ、お前が
やれといろいろやったが、みんな逃っ尻をかまえていてやりたがらなか
ったナー、仕様がなくて「ヨシダ」の爺さんに頼んでやってもらったのサ。
それが終いには「ヨシダ」の爺さんの役のようになったナー。今のように
色々の入れ物も無かったし、手桶で水をかけたが、そこまであまり届か
なかったニ、若い衆は爺さんが岩から降りて来ると「オマケ」だといって、
また浴びせかけて面白がったニ。
ある日、今日昼から雨乞いをやろうじゃと、話があったが、こんな日にや
ったって雨なんか降るもんか、といって出ずに居たら、後で八分にあっ
たニ』
安良里の藤井寅吉(故人)さんの語り口...
『アノ岩は大部埋まったニ、まァだ三尺(約1メートル)位い高かったナー
雨乞いの話は聞いているが、俺ァ、あっこでやった覚えはないナー』
資料は宇久須の海鮮焼き「かねじょう」店主の浅賀丈吉さんからお借りしました。
Posted by 鈴木達志 at 08:16│Comments(1)
│安良里
この記事へのコメント
始めまして~
元、安良里住人です
私達学生の頃は、雨降り石はみんな
知っていましたよ~
体育祭の前の日なんかに、良く入れてました
元、安良里住人です
私達学生の頃は、雨降り石はみんな
知っていましたよ~
体育祭の前の日なんかに、良く入れてました
Posted by うさばば at 2007年07月21日 00:41
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。